【量子力学】スピノルとスピノル代数
【量子力学】スピノルとスピノル代数
物理・数学ノート>量子力学
■はじめに
ここではスピノルとその基本的な性質について解説する。 まず、スピン1/2を持つ粒子の波動関数を記述するために、1階のスピノルを導入する。 その後、テンソル代数とのアナロジーでスピノルに関する代数を構築し、そこからスピノルと、ベクトルやより高階のテンソルとの関係を調べる。 前半の内容については、群論の文脈で同様の内容を解説した『スピノル:$SO(3)$と$SU(2)$の対応』も参照のこと。
■スピノルとその変換
スピン$s=1/2$の粒子を考える。 波動関数は、それぞれスピンの値$1/2$と$-1/2$に対応して$\psi^1=\psi(1/2)$と$\psi^2=\psi(-1/2)$の2成分を持ち \begin{align} \label{eq:psi_spin1/2} \psi= \left( \begin{array}{c} \psi^1 \\ \psi^2 \end{array} \right) = \left( \begin{array}{c} \psi(1/2) \\ \psi(-1/2) \end{array} \right) \end{align} と表せる。
座標回転に伴う変換は、$2\times 2$行列 \begin{align} \label{eq:U_matrix} U= \left( \begin{array}{cc} a & b \\ c & d \end{array} \right) \end{align} によって \begin{align} \label{psi'} {\psi^1}'=a\psi^1+b\psi^2, \quad {\psi^2}'=c\psi^1+d\psi^2 \end{align} の形に表現できる。 以下、この変換行列の性質をもう少し詳しく調べてみよう。
そのためにまず、2つのスピン$1/2$の粒子(それぞれの波動関数を$\psi$および$\varphi$と記す)からなり、合成スピンが0の状態にある系を考える。 この状態は一方の粒子が値$1/2$、もう一方の粒子が$-1/2$を取る場合に対応するため、粒子間の相互作用を無視できるとすれば、この系の波動関数は \begin{align} \phi = \frac{1}{\sqrt 2} (\psi^1 \varphi^2 -\psi^2\varphi^1) \end{align} と書ける。 $1/\sqrt2$は規格化のための係数である。
スピン0の系の波動関数はスカラーであるから、成分の組み合わせ \begin{align} \label{eq:psi_scalar} \psi^1 \varphi^2-\psi^2\varphi^1 \end{align} はスカラーとなる。 (\ref{eq:U_matrix})による$\psi,\varphi$の変換 \begin{align} \notag \psi\to& \psi' =U\psi, \\ \varphi\to& \varphi'=U\varphi \end{align} により、(\ref{eq:psi_scalar})は \begin{align} {\psi^1}' {\varphi^2}' -{\psi^2}'{\varphi^1}' = (ad-bc) (\psi^1 \varphi^2-\psi^2\varphi^1) \end{align} と変換されるが、(\ref{eq:psi_scalar})がスカラーであるということ、すなわち座標変換の下で不変であるという条件から \begin{align} ad-bc=1 \end{align} でないといけないことがわかる。
一方、粒子の確率密度 \begin{align} |\psi^1|^2+|\psi^2|^2 = \psi^1\psi^{1*} + \psi^2\psi^{2*} \end{align} もまたスカラーであるから、(\ref{psi'})とその複素共役より \begin{align} U^\dagger =U^{-1} \end{align} であること、すなわち、$U$がユニタリー行列である必要があることがわかる。
こうして、スピン1/2の粒子の波動関数(\ref{eq:psi_spin1/2})は、座標の回転に伴い、行列式が1である2次のユニタリ行列によって変換されることがわかった。 このような行列の集合を$SU(2)$、(\ref{eq:psi_spin1/2})のように$SU(2)$の元によって変換される2成分ベクトルをスピノル(spinor)という。
■計量テンソルと縮約
上で導入したスピノルにいくつかの概念を加えることで、テンソル代数と類似の代数を構築することができる。 まず、添え字を上に持つ反変スピノルに加え、下付き添え字の共変スピノルを導入する。
テンソル代数とのアナロジーで、スカラー \begin{align} \notag \psi^1 \varphi^2-\psi^2\varphi^1 \end{align} を2つのスピノルの縮約$\psi^\mu \varphi_\mu=\psi^1\varphi_1+\psi^2\varphi_2$によって表現しようと思えば \begin{align} \psi_1=\psi^2, \quad \psi_2=-\psi^1 \end{align} によって共変成分を定義すればよいと分かる。
これは計量 \begin{align} g_{\mu\nu}= g^{\mu\nu}= \left( \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{array} \right) \end{align} を導入することに対応する。 すなわち、これによってスピノルの添え字の上げ下げが \begin{align} \psi_\mu=g_{\mu\nu}\psi^\nu, \quad \psi^\mu=g^{\mu\nu}\psi_\nu \end{align} のように行われる。
■高階のスピノル
縮約と並ぶテンソル代数におけるもう1つの基本的な演算は、縮約によってランクを下げるのとは反対で、積により高階のテンソルを作ることである。 以下これとの類推で、高階のスピノルを導入する。
例を示すために、2つの電子からなる系で、今度は合成スピンが1である状態を考よう。 この場合、取りうるスピンの値は$1,0,-1$の3通りあり、波動関数の対応する成分はそれぞれ \begin{align} \label{eq:spinor_spin1} \psi^1 \varphi^1, \quad \frac{1}{\sqrt 2}(\psi^1 \varphi^2+\psi^2\varphi^1), \quad \psi^2 \varphi^2 \end{align} の形で表せる。
これらはみな、1階のスピノルの積により作られ、添え字に対して対称な量となっている。 一般に、1階のスピノルの積と同様の変換をする量を2階のスピノルといい、$\psi^{\mu\nu}$と表す。 特に、添え字に対して対称なものを、2階の対称スピノルという。
座標回転に対する合成スピン1の2電子系の波動関数の振る舞いは、スピン1の単一粒子系のものと同様であるから、スピン1の系の波動関数は一般に2階の対称スピノルによって表現することができる。 同様に、任意のスピン$s$を持つ系は$2s$階の対称スピノルによって表現できる。 よって、対称スピノルを用いることで、座標回転に対する変換に応じて量を分類することができる。 テンソルでは整数スピンを持つ粒子しか記述できないため、スピノルはその意味でテンソルよりも基本的な量であるといえる。
対称スピノルの場合$\psi^{12}=\psi^{21}$であるから、波動関数の成分$\psi(\sigma)$と2階の対称スピノルとの関係は(\ref{eq:spinor_spin1})より
\begin{align}
\label{eq:psi_s=1}
\psi(1)=\psi^{11},\quad
\psi(0)=\sqrt{2}\psi^{12},\quad
\psi(-1)=\psi^{22}
\end{align}
となる。
スピン$s$の波動関数は$2s$階のスピノル$\psi^{\mu\nu...}$によって表すことができ、波動関数の成分とスピノルを
\begin{align}
\sum_{\sigma=-s}^s |\psi(\sigma)|^2
=
\sum_{\mu,\nu...=1}^2 |\psi^{\mu\nu...}|^2
\end{align}
が成り立つように結び付ければ
\begin{align}
\label{eq:psi_sigma}
\psi(\sigma)
=
\sqrt\frac{(2s)!}{(s+\sigma)!(s-\sigma)!}
\psi^{\underbrace{11,...,1}_{s+\sigma}\underbrace{22,...,2}_{s-\sigma}}
\end{align}
のように係数を決めればよいと分かる。
実際、例えば$s=1$の場合
\begin{align}
\sum_{\sigma=-1}^1 |\psi(\sigma)|^2
=&
|\psi(-1)|^2+|\psi(0)|^2+|\psi(1)|^2 \notag \\
=&
|\psi^{11}|^2+2|\psi^{12}|^2+|\psi^{22}|^2
\end{align}
より、(\ref{eq:psi_s=1})と一致する結果が得られる。
■1階の対称スピノルとベクトル
さて、任意のスピン角運動量$s$を持つ状態は、その構成にかかわらず、階数$2s$のスピノルによって表現できるのであったが、この議論はさらに一般化出来て、$s$を軌道角運動量を含む全角運動量で置き換えても同様に成り立つ。 よって(\ref{eq:psi_sigma})を一般化することで、全角運動量$l$を持つ系の波動関数を \begin{align} \label{eq:phi_lm} \phi_{lm} = \sqrt\frac{(2l)!}{(l+m)!(l-m)!} \psi^{\underbrace{11,...,1}_{l+m}\underbrace{22,...,2}_{l-m}} \end{align} と表すことができる。 ここで、$m=l,l-1,...,-l$である。
整数の角運動量$l$の固有関数は、球面調和関数$Y_{lm}$で与えられるのであった。 $l=1$の場合 \begin{align} Y_{10} =&\sqrt\frac{3}{4\pi}\cos\theta =\sqrt\frac{3}{4\pi}n_z, \notag \\ Y_{1\pm1} \label{eq:Y1m} =&\sqrt\frac{3}{8\pi}\sin\theta e^{\pm i\phi} =\sqrt\frac{3}{8\pi}(n_x\pm in_y) \end{align} の3つがある。 ここで、位置ベクトル$\bm{r}=(x,y,z)$に対し$\bm{n}=\bm{r}/|\bm{r}|=(n_x,n_y,n_z)$で、$\phi$は3次元極座標における方位角である。
このことから、これら3つの関数は、変換に関してベクトル$\bm{a}=(a_x,a_y,a_z)$の成分と \begin{align} \phi_{10}=a_z,\quad \phi_{1\pm1}=\frac{1}{\sqrt 2}(a_x\pm ia_y) \end{align} の関係で結ばれる。 さらに、(\ref{eq:phi_lm})と比べることで、ベクトルと2階の対称スピノルの関係が \begin{align} \psi^{12} =&\frac{1}{\sqrt 2}\phi_{10} =\frac{1}{\sqrt 2} a_z, \notag \\ \psi^{11} =&\phi_{11} =\frac{1}{\sqrt 2}(a_x+ ia_y), \\ \psi^{22} =&\phi_{22} =\frac{1}{\sqrt 2}(a_x-ia_y) \notag \end{align} と得られる。 また、逆に解くことで \begin{align} a_z=&\sqrt 2 \psi^{12}, \notag \\ a_x=& \frac{1}{\sqrt 2}(\psi^{11}+\psi^{22}), \\ a_y=& -\frac{i}{\sqrt 2}(\psi^{11}-\psi^{22}) \notag \end{align} の関係も得られる。
■参考文献
-
Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (1981). Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory (Vol. 3). Elsevier.
――(1983), 量子力学―非相対論的理論 (1) (ランダウ=リフシッツ理論物理学教程). 佐々木健, 好村滋洋 訳. 東京図書. - Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (1974). Quantum Mechanics: A Shorter Course of Theoretical Physics. Pergamon.
――(2008). 量子力学―ランダウ=リフシッツ物理学小教程. 好村滋洋, 井上健男 訳. 筑摩書房. - Tinkham, M. (2003). Group theory and quantum mechanics. Courier Corporation.
- Tung, W. K. (2003). Group Theory in Physics: An Introduction to Symmetry Principles, Group Representations, and Special Functions in Classical and Quantum Physics. World Scientific Pub. Co. Inc.
物理・数学ノート>量子力学


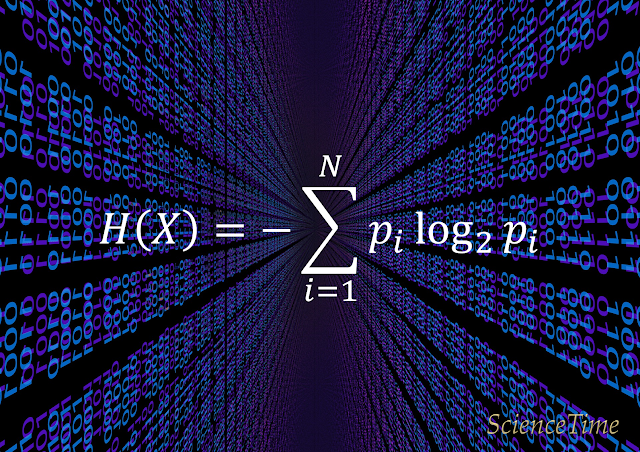



コメント